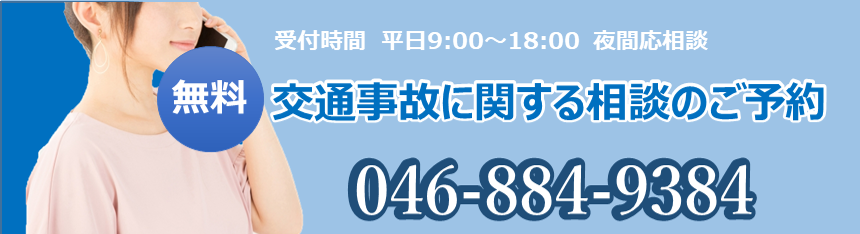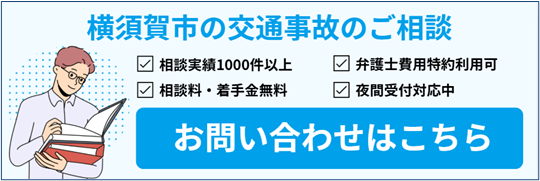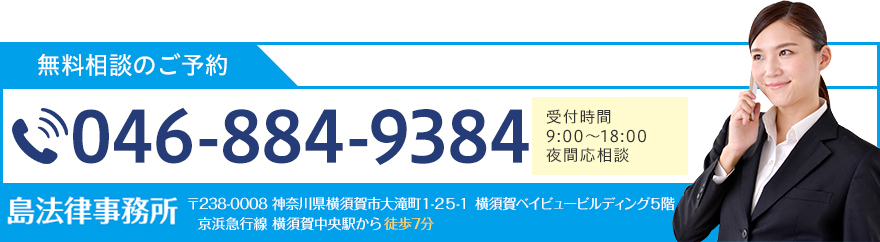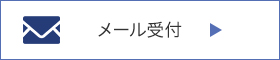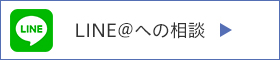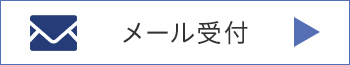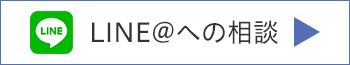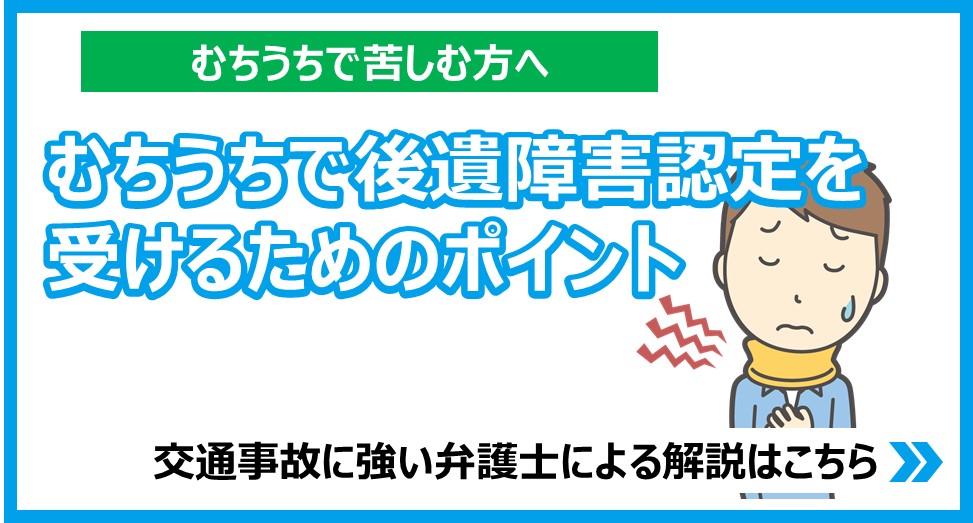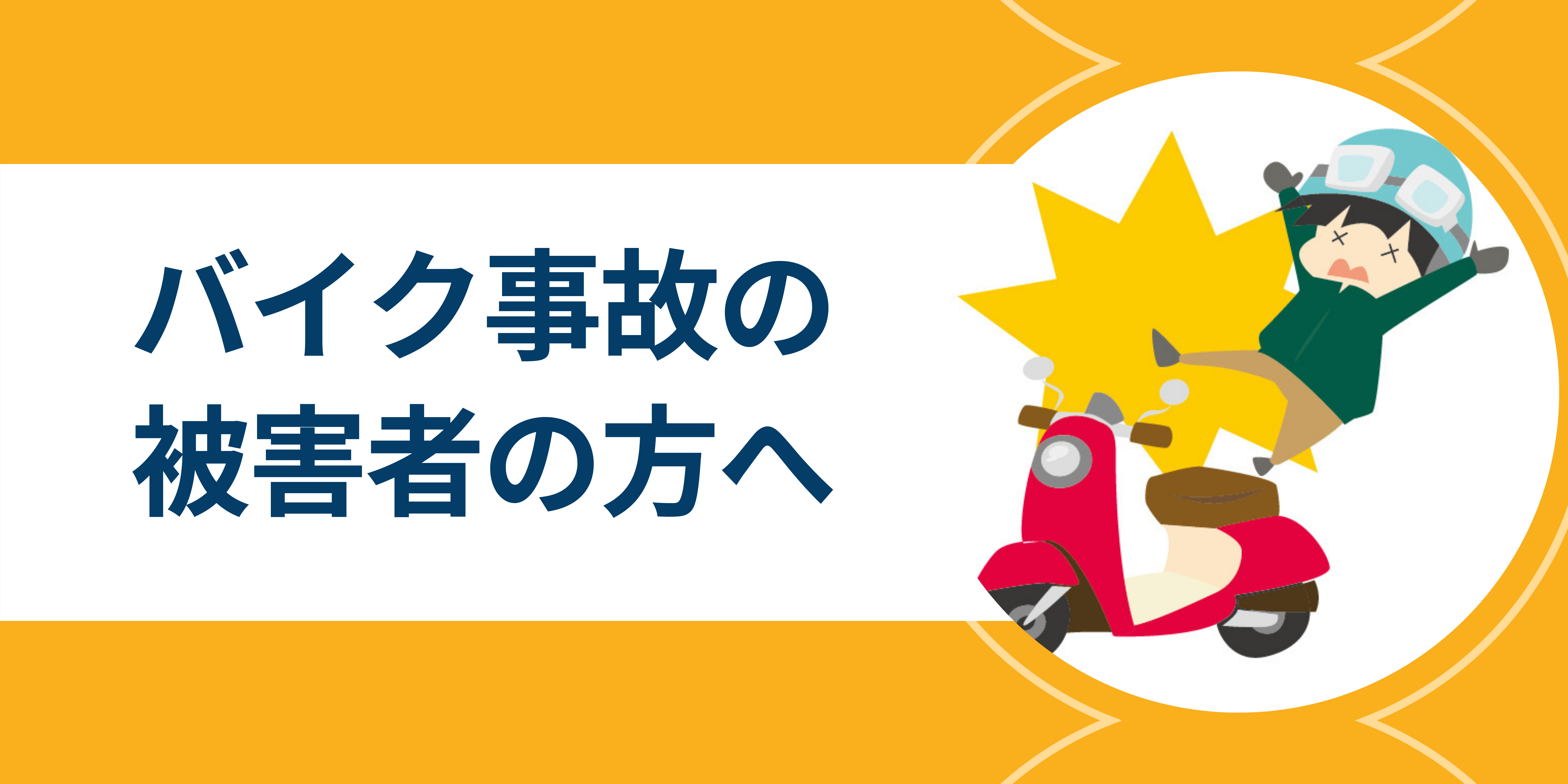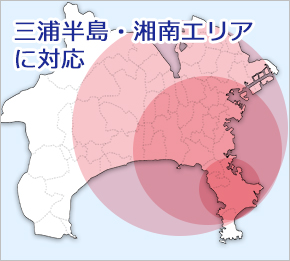聴覚障害の後遺障害等級について
後遺障害等級とは、後遺障害の重さのことで、一番重い第1級から第14級まであります。
聴覚障害が該当するのは、4~14級です。
どのような症状が現れているのかによって、認められる可能性がある等級が変わります。
以下で詳しく説明していきます。
聴覚障害の後遺障害等級
聴覚障害が残ってしまった方が認定される可能性がある後遺障害等級は、4~14級です。
- 両耳に聴覚障害がある場合:4級〜11級
- 片耳のみに聴覚障害がある場合:9級〜14級
- 聴覚障害に伴って耳鳴りがある場合:12級・14級
となります。
両耳に聴覚障害がある場合
4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
9級7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
11級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの
片耳のみに聴覚障害がある場合
9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの
1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの
11級6号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの
聴覚障害に伴って耳鳴りがある場合
12級 耳鳴が常時あると評価できるもの
14級 医学的に合理的に耳鳴りの存在を説明できるもの
聴覚障害で適正な等級の認定を受けるためにやるべき4つのこと
- 後遺障害認定に必要な聴力検査を行う
- 気になる症状はすべて主治医に伝える
- 適切なタイミングで症状固定の診断を受ける
- 交通事故に強い弁護士のアドバイスを受ける
以下説明します。
1. 後遺障害認定に必要な聴力検査を行う
適正な後遺障害等級の認定を受けるには、認定基準に対応した聴力検査を受けておくことが重要です。
なぜなら、聴覚障害の有無やその程度は、検査結果をもとに判断されるからです。
両耳、片耳の聴覚障害:
- 標準純音聴力検査:どれだけ小さい音まで聞こえるかを調べる検査(聞こえの程度は正常か、どの程度の聞こえの悪さかを判断する)
- 語音聴力検査:言葉をどの程度明確に聞き取れるかを確かめる検査
耳鳴りを伴う聴覚障害:
- ピッチ・マッチ検査:機械を使って音を流し、耳鳴りの周波数を調べる検査
- ラウドネス・バランス検査:耳鳴りがどのくらいの音量なのかを調べる検査
- 耳鳴マスキング検査:耳鳴りと似た音を出して、耳鳴りの聞こえ方を確かめる検査
これらの検査を受けることを検討してください。
2. 気になる症状はすべて主治医に伝える
後遺障害の等級認定を正しく受けるためには、どんなに小さな症状でも主治医にすべて伝えておくことが大切です。
診断書には、「いつからどの程度の症状がでているのか」といった自覚症状の経過も記載され、等級の判定に影響します。
自覚症状は、医師にとっても重要な判断材料です。
伝えるほどでもないかもと思う症状でも、遠慮せず必ず主治医に話してください。
3. 適切なタイミングで症状固定の診断を受ける
適切なタイミングで症状固定の診断を受けることも、聴覚障害で適正な等級の認定を受けるために必要です。
症状固定とは、交通事故において治療終了を意味するものです。
主治医が交通事故に詳しくないケースもあるので、症状固定の診断を受ける際は医師に任せきりにせず、「今が適切なタイミングなのか」を自分でも確認しましょう。
4. 交通事故に強い弁護士のアドバイスを受ける
聴覚障害で適正な等級を認定してもらうには、できるだけ早い段階で交通事故に強い弁護士に相談することが大切です。
交通事故に強い弁護士がいれば、聴覚障害の等級認定に必要な証拠を漏れなく集められるからです。
専門知識が求められる聴覚障害の後遺障害
以上、聴覚障害の後遺障害等級について説明してきました。
わかりづらく、弁護士でも専門的知識が求められる事案です。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
交通事故を多数扱って、多数の後遺障害等級を獲得してきた経験とノハウから適切なアドバイスをさせていただきます。
運営者情報
- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
-
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
弁護士紹介はこちら
最新の投稿
- 2025.12.23交通事故で歯が折れときの後遺障害について
- 2025.12.23交通事故で遷延性(せんえんせい)意識障害になったら?後遺障害や損害賠償について詳細に弁護士が解説
- 2025.11.27非接触事故でも慰謝料を請求できるか
- 2025.11.27主婦の休業損害について
横須賀での交通事故にお悩みの方は
今すぐご相談ください
-
提示された示談金が
低すぎる -
適切な後遺障害等級の
認定を受けたい -
保険会社の対応に
不満がある -
過失割合に
納得がいかない -
治療費の打ち切りを
宣告された -
どのように弁護士を選んだら
いいのか分からない -
追突事故
-
バイク事故
-
死亡事故